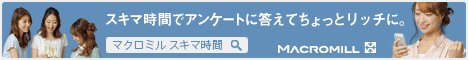ぺロポネソス戦争後のギリシア世界
ペロポネソス戦争により、アテネに代わってスパルタがギリシア世界のリーダー格となりましたが、スパルタはギリシア世界を統率することが難しく、有力ポリスらの覇権争いが続きました。ここでは、ペロポネソス戦争後のギリシア世界の推移を見ていきたいと思います。
アテネ三十人僭主政と民主政の復活
ペロポネソス戦争後のアテネを支配したのは、スパルタの支持を得た寡頭政派でした。寡頭政派の中でも30人の代表が選ばれ、彼らにによって政権が運営されました。この政治体制は「三十人僭主」と呼ばれています。主だったメンバーには、クリチアス(Kritias 56歳前後)、テラメネスなどがいます。クリチアスは多才な人物で、修辞家としても詩人としての能力も高く、また哲学者でもありました。古代ギリシアの代表的な哲学者・プラトンの母は、クリチアスのいとこにあたります。三十人僭主は、父祖伝来の新しいアテネ国制を作り上げるという名目で選ばれていますが、その実態はスパルタ軍の力を頼みとした恐怖政治でした。三十人僭主はまず民衆法廷の権限を奪って裁判権を独占すると、反対派の人々を次々と捕えては処刑し、その財産を没収するという、恐るべき世の中になってしまいました。やがて、三十人僭主の中で派閥争いが始まり、比較的穏健派であったテラメネスは、過激派代表格のクリチアスに殺害されています。
しかし、三十人僭主体制は長続きしませんでした。民主政を支持するトラシュブロスらが、前403年に三十人僭主打倒のために蜂起し、パルネス山の要塞を占拠。さらに、外港ピレウスに入り、三十人僭主の軍と交戦して勝利しました。クリチアスはこの戦いで戦死し、残った僭主らは逃亡。アテネには民主政が復活しました。
クセノフォンの退却行 「アナバシス」
ギリシア世界のライバルであるアケメネス朝ペルシアで、前401年に王位継承争いが起りました。アケメネス朝ペルシアの王・ダレイオス2世(Dareios II 生年不詳)が前404年に死去すると、後継者として息子のアルタクセルクセス2世(Artaxerxes II 生年不詳)が王に即位しました。ところが、これに反抗したのが異母弟のキュロス(Kyros 生年不詳)です。キュロスは小アジアのサトラップとして、当時はまだ20歳少々でしたが利発で賢いという評判を受けて将来を嘱望されていました。キュロスは、自分こそアケメネス朝の王にふさわしいと考え、前401年に遠征軍を招集するという口実で、謀反のための軍隊を集めました。これに応えたのが、ペロポネソス戦争以降、職を無くして路頭に迷っていたギリシア人達です。もともと、耕地が少なかったギリシアでは、職にあぶれる男たちが多かったので、外国で傭兵として稼ぐ男たちが一定数いたと考えられています。ぺロポネソス戦争で、ギリシアが荒廃から復興する過程の中にあったギリシアでは、外国に出て傭兵稼業で稼ごうと考える男達が多くいたそうです。彼らにとって、アケメネス朝がギリシアの敵国であることなどは、あまり関係のないことでした。
キュロスは、ギリシア人傭兵多数を含む総勢1万3000ほどの軍を率いて東に向かいました。ユーフラテス川に到着すると、キュロスは兵士たちにアルタクセルクセス2世討伐を行う旨を表明し、首都・スーサに向かって軍を進めました。キュロスの謀反を知ったアルタクセルクセス2世は、迎撃の軍を送り出し、両軍はユーフラテス川左岸、バビロンの北方に位置するクナクサで激突しました。クナクサの戦い(Battle of Cunaxa)です。この戦いは、ギリシア人傭兵の活躍もあり、開戦当初からキュロス軍優勢で進みました。キュロス自身も、600の騎兵を率いて戦闘に参加しましたが、なんとキュロスはこの時の戦闘で戦死。優勢だったキュロス軍は、大将の突然の戦死の報を聞いて総崩れとなり、キュロス軍は大敗北を喫しました。
戦場から落ち伸びたギリシア人傭兵は、敵地に取り残されて絶体絶命の危機に陥ります。そんな時、ギリシア人傭兵らに指揮官として選ばれたのがクセノフォン(Xenophon 29歳前後)です。クセノフォンは、1万人のギリシア人傭兵を率いてバビロン付近の砂漠から、アケメネス朝の追手や自然の猛威と戦いながら、北に向かってアルメニアを通過し、黒海に至ります。ここから西に向かってようやく地中海に到達し、折しも小アジアに攻め込もうとしていたスパルタの将軍・チブロンに全軍を委ねることができました。クセノフォンは、この時の記録を自著『アナバシス(内陸行、の意)』に詳しく記録しています。『アナバシス』は、当時のギリシア人重装歩兵の訓練度の高さを知る貴重な史料となっている他、アルメニア地方や黒海沿岸部の住民の風俗や地誌などについても、多くの記述を残しており、クセノフォンの文筆家としての名声の根拠になっています。
ソクラテスの死
古代ギリシアの哲学者として、最も有名なのがはおそらくソクラテス(Sokrates)でしょう。ソクラテスは前470頃、父は彫刻家(石工とも)のソフロニスコス、母は助産師のファイナレテの子としてアテネに生まれました。ソクラテスの前半生はほぼ不明となっていますが、哲学者としての道を歩み始めたきっかけとなったのは、「汝自身を知れ」というデルフォイの神託でした。ソクラテスの思考の出発点は
人間の知恵は、神には到底及ばないものなので、自己が無知であることを知る哲学的反省が肝要である
というものでした。ソクラテスが他の哲学者とやや違っていたことは、アテネの人々に積極的に語りかけて、この信念を実践していったことにあります。その方法は、「私は何も知りません」と言って相手に質問を投げかけることから始り、相手が答えると、さらに質問を重ねて深堀りしていくということでした。こうすることで、相手はやがて論理的に行き詰ってしまい、自分には答えられない部分があることを自覚させたり、あるいは普段は当たり前と思っていて、特に考えていなかったことに気づかせる、というものでした。この方法は、ソクラテスの母が助産師であったことから「産婆術」と呼ばれたりしています。現代のビジネスの世界でも、このような方法は問題発見や問題解決の方法を探る方法として活用されています(例えば、トヨタ自動車の「なぜなぜ運動」など)。
このように、相手との対話を通じて、相手に何かを気付かせるという方法で、ソクラテスには多くの弟子がつきました。例えば、哲学者ではプラトンがおり、前段のクセノフォンもソクラテスの弟子です。そして、ペロポネソス戦争で活躍(?)したアルキビアデスもソクラテスの弟子の一人でした。ペリクレスの愛人であったアスパシアもソクラテスとよく対話をしたそうです。
ただ、このような方法に敵意を持つ人々もいました。当時「ソフィスト」と呼ばれていた、弁論術などを教える講師達です。民主政アテネでは、民会における演説がとても重要な役割を持っていました。演説で、いかにして多くの市民から同意を得ることができるかどうかが、政治家としての大切な能力だったのです。これは、アケメネス朝ペルシアのような専制君主制の国では、なかなか見られない特徴です。そのため、相手を説得する、相手に自分の意見の正しさを主張する弁論術は、たいへん需要がある技術でした。ソクラテスは弁論術のようなテクニックは、彼が考える「真の知恵」とは異なるものとし、ソフィストたちに対してもいつもの「対話」を行い、しばしば弁論術の先生を論理で窮地に追い込みました。
ソクラテスのもう一つの特徴は、著作を一切残さなかったことです。そのため、現代人が知っているソクラテスの思想については、弟子のプラトンやクセノフォンの記録に基づいたものなのです。もし、ソクラテスの著書を発見することができたら、世界史や哲学史の世界の一大発見となると思います。
前399年(ソクラテス71歳前後)、メレトスとアニュトス(Anytos 生没年不詳)らはソクラテスを涜神罪で告発しました。彼らが言うには、ソクラテスは神々を信じないばかりか、新しい神を導入し、青年達に悪影響を与えた、とのことです。ソクラテスは法廷で裁判にかけられましたが、告発にたいして堂々と弁明を行いました。しかし、陪審員らの同意は得られず、ソクラテスには死刑が宣告されたのです。ソクラテスは、毒が入った杯をあおってその生涯を閉じました。
コリント(コリントス)戦争
ペロポネソス戦争終結後、アケメネス朝ペルシアはスパルタと交わした密約のとおり、小アジアのギリシア人植民都市に干渉を始めました。これに対し、スパルタ王・アゲシラオス2世は軍を率いて小アジアに上陸し、アケメネス朝の軍に攻撃を始めました。これに対しアケメネス朝は、銀貨50タラントを有力ポリスの指導者らに贈り、反スパルタ同盟を結成するように呼びかけました。これに応えたのが有力ポリスの一つ、テーベです。コリント、アルゴス、アテネなどもテーベと共に反スパルタで蜂起し、戦争となりました。この戦争はコリント(あるいはコリントス)戦争と呼ばれ、前395年から前386年まで続きました。この戦争の最中の前393年、アケメネス朝はアテネに支援金を贈り、その資金でアテネは海軍力を回復させるきっかけとなった他、アテネ市とピレウス港を結ぶ城壁が再建されました。
これに対し、スパルタの将軍・アンタルキダスは、アケメネス朝とシラクサの援助を取り付けてアテネの復権を阻止すると共に、諸ポリスの動きを牽制。前386年にアケメネス朝とギリシア諸ポリスの間に「アンタルキダスの和約(大王の和約、とも)」と呼ばれる条約を結びました。前386年、ギリシア諸ポリスの使者が小アジアのサルディスに召集され、「アンタルキダスの和約」を強制させられました。この和約の内容は、小アジアのギリシア人植民都市の支配権はアケメネス朝ペルシアに割り当てられるという、売国的な条件でした。このため、ギリシア世界における反スパルタの気運はますます強くなっていきます。
プラトンとアカデメイア
コリント戦争も終盤に差し掛かった前387年、プラトン(40歳前後)はアテネの西郊外に学校を開設しました。この学校は英雄アカデモス神にちなんで「アカデメイア」と名付けられました。プラトンは前428(or 427)年、アテネの名門に生まれました。若き日のプラトンは、42歳年上のソクラテスの思想にいたく感動し、哲学の世界に足を踏み入れました。
「哲学と合理的思考の夜明け」でも書いているように、古代ギリシアの哲学の特徴は、実験による事実の検証ではなく、事実を説明する理論の形成にありました。その代表例の一つが、プラトンのイデア論です。
プラトンはアテネの貴族の家系に生まれ、当初は政治の世界で活躍しようとしますが、師匠であるソクラテスを死刑とした民主政アテネの姿に幻滅し、政治の世界から去って行きました。この経験がプラトンを現実世界を軽視し、完全なる存在である思考の世界へと導いたのかもしれません。プラトンは、ソクラテスからピタゴラス哲学や倫理問題に対する理想主義的な思考、「ディアレクティケー(問答法、弁証法)」などを学びました。「真」「善」「美」という重要なイデアは、ディアレクティケーと直観によって発見できる、というのがプラトンの考えでした。「イデア」とは、永遠で不変の世界に存在する「真の実体」といえる概念です。イデアで構成された真実の世界は、感性で知覚できるものではなく、魂によって近づけると考えました。感覚は人間を欺き間違った方向に導きますが、魂は理性を用いることでイデアを理解できる、としました。この思想は、後のキリスト教における「霊肉二元論」などに影響を及ぼしました。人間は神から授かった魂と、魂の牢獄である肉体という二つの要素に分離できるとするキリスト教の思想です。
その一方で、プラトンは現実社会の問題である「国家の体制」についても大きな関心を持っていました。それを表現したのが『対話篇』と呼ばれるプラトンの一連の著作です。これは、史上初の哲学のテキスト、とも言えます。対話篇は、ソクラテスとソクラテスを訪れた人々の会話という形式で構成されています。その中の作品の一つ『国家』では、社会の仕組みとその倫理的な目標について体系的に述べられています。「国家」の中で理想とされているのは、スパルタのような全体主義国家でした。その理想国家では、優秀な遺伝子を残すために結婚がコントロールされ、家族や私有財産といった考え方は存在せず、文化と芸術は検閲を受けなければならず、教育も厳しく管理されます。この国家はごく少数の人間に統治され、統治者らはイデアの世界を理解し、正しい社会を実現するために必要な知恵を持つことが義務付けられました。知恵とは本質を理解する力のことであり、人は真実を見ることさえできれば、必ずそれに従って行動するはずだ、と考えていました。プラトンが理想とした国家は、大多数の人が教育と法律によって管理される生活を強いられています。師匠のソクラテスは、そのような生活を「エレンコス(吟味、の意)のない生活」として生きるに値しないと評価していました。プラトンは、ソクラテスの多くを踏襲しましたが、この点については全く異なる見解をとりました。
プラトン以降の西洋哲学は「事実上すべてプラトンの脚注」と評価する哲学者いるくらい、後の世に大きな影響を与えました。プラトンの思想には、倫理、美意識、知識の根拠、数学の本質など、哲学の重要な命題を含んでおり、さらにそれらの思想を対話といる理解しやすい形で残したことが、その影響力の大きさの源泉となったといえます。
レウクトラの戦い
スパルタの次にギリシア世界の覇者になったのは、コリント戦争で反スパルタの旗手となったテーベでした。それが決定的となったのが、前371年のレウクトラの戦いです。テーベ軍は歩兵7000、騎兵1000を名将・エパミノンダス(エパメイノンダス、とも。"Epameinondas" 39歳前後)が率い、対するスパルタは歩兵1万をスパルタ王・クレオブロトスが率い、両軍はボイオティア平原のレウクトラで決戦に臨みました。
エパミノンダスは「斜線陣」と呼ばれる新戦術を実践しました。斜線陣は、自軍戦力を左翼に集中させて、中央と右翼は戦力が少ない分、左翼よりも後方に配置させるというものでした。中央と右翼の役割は、敵を引きつけて時間を稼ぐことにありました。そのため、なるべく後方に配置し、接敵するまでの時間を稼いだものと思われます。そして、戦いの決め手となるのが、戦力を集中させた左翼です。左翼は敵軍に攻撃を仕掛けて粉砕し、その後中央と右翼に引きつけられている敵軍を背後から攻撃して、包囲殲滅するという戦法でした。この新戦術は大成功し、陸戦では無敵と評価されていたスパルタ軍は壊滅的な損害を被り、指揮官のクレオブロトスも戦死ています。ほぼ同等の戦力の戦いで、スパルタが完敗したというこの戦いは、古代ギリシア世界の終わりを象徴する一つの事件と言えます。
レウクトラの勝利でスパルタの軍事力は大きく低下し、テーベはスパルタ領であるペロポネソス半島の内部に侵入し、メッセニアやアルカディアといったスパルタが支配していたポリスを攻略し、独立させました。これにより、テーベはギリシア世界の新しいリーダーとなったわけです。しかし、その覇権は長続きしませんでした。前362年のマンティネイアの戦いでエパミノンダスが戦死するとテーベの覇権は失われ、ギリシア世界は再び諸ポリスが互いにしのぎを削る分立抗争の時代になります。それからしばらく後、ギリシア世界は北方の王国・マケドニアの旗の下に統合され、ギリシアとしての独立性を徐々に失っていきました。
アリストテレスと「中庸」
プラトンが設立したアカデメイア学園で学んだ学生の一人が、アリストテレス(前384年〜322年)です。ソクラテス―プラトン―アリストテレスという古代ギリシア三大哲学者は、師弟関係で繋がっているわけですね。思考の世界に集中した師匠・プラトンと異なり、生物学に興味を持ったアリストテレスは大量のデータを収集・分類することを重要な方法論としました。現実世界から得られた情報を基盤とし、個別の事実から法則を導き出すという、帰納法を展開させていきました。アリストテレスは「万学の祖」と呼ばれることもあるほど、現実世界の様々な分野に関する著作を残しました。後世に与えた影響を主なものだけ列挙してみても、中世スコラ哲学、生物学、物理学、数学、論理学、文芸批評、美術、心理学、政治学など、実に幅広いのが特徴です。そして、これらの分野の思考法や研究方法を体系化したことが、最大の功績だと言えます。アリストテレスの思想体系は中世スコラ哲学にも採用され、演繹的論理学は19世紀末まで受継がれていきました。
アリストテレスの重要な考え方の一つに「中庸(ちゅうよう)」があります。アリストテレスも師匠のプラトンと同様に、理想的な国家とはポリスであり、ポリスが正しく機能するためには絶えざる自己改革と節度だと考えていました。ただ、アリストテレスは国家の理想的な状態を「中庸(行きすぎでも不足でもない、の意)」と考えたのです。両極端な考えを排した心の状態こそ、ポリス市民が持つべき「品性の徳」だとしたのです。この思想が正しいことを裏付けるために、アリストテレスは150近いポリスの国家制度と歴史を体系的な形で収集しました。現在ではそのほとんどが失われてしまっているというのは、非常に残念なことです。
なお、アリストテレスについてもう一つ重要なことがあります。マケドニア王国からアレクサンドロス3世の家庭教師として招かれました。アレクサンドロス3世は、後にアレクサンドロス大王と呼ばれる人物です。
こうして、世界史の主役はギリシアからマケドニアに移っていきました。
| 前404年 | |
| アテネに三十人僭主が君臨する。 | |
| 前403年 | |
| トラシュブロスら民主派が三十人僭主を打倒し、民主政アテネが復活。 | |
| 前401年 | |
| クナクサの戦いでキュロスが敗北。残されたギリシア人傭兵らをクセノフォンが率いてギリシアに脱出する。 | |
| 前399年 | |
| ソクラテスに神を冒涜した罪で死刑判決が下される。 | |
| 前395年 | |
| コリント戦争 開戦 | |
| 前387年 | |
| プラトンがアカデメイアを設立 | |
| 前386年 | |
| アンタルキダスの和約 | |
| 前371年 | |
| レウクトラの戦いでテーベがスパルタに大勝 | |
前へ戻る(12.ペロポネソス戦争 後篇)
古代ギリシア 目次へ戻る